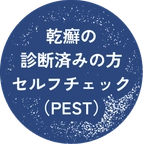日々お悩みの
痛みについて

痛みをどのように考えていくか
乾癬性関節炎の診療を考えていくうえで、「痛みに対する対応」は最も重要な課題といっても過言ではありません。MDA(最小疾患活動性)の治療目標の7項目の中で、最も達成しにくいのが、「痛み」の項目といわれています。
「痛み」の原因は様々ですが、大きく分けると、「炎症を伴うもの」と「炎症を伴わないもの」に分けられます。
炎症を伴う痛み
いわゆる関節(骨と骨とがつながる部位)の内張をなす関節滑膜の炎症が、代表的な痛みの原因となります。しかし、乾癬性関節炎の場合、他の部位にも炎症を起こすことがしばしばです。
たとえば、腱や靭帯が骨に付着している付着部に炎症が起きます。ここは、いわゆる関節から少し外れた部分の痛みとなります。この部分は、いわゆる「使い痛み」でも痛くなる部分ですが、「使い痛み」なら安静で2週間程度でおさまりますので区別が可能です。
とくに手指は腱や靭帯が密に分布していますので、この「付着部炎」が集合して「指炎」といわれる状態になることがあります。指が紡錘状に腫れて、継続する痛み、こわばりを感じるようになります。
手指に並んで靭帯が密に分布しているのが、脊椎(背骨)です。脊椎の付着部に炎症があるときは、常に痛みを感じることが多いと思われますが、とくに安静後の動き始めの痛みが強いことが特徴となります。
付着部から炎症が腱、腱鞘にまで波及しますと、「腱鞘炎」としての痛みを感じるようになります。動かしたときの痛み、腱に沿った痛みや腫れが特徴です。
これらの諸部位の痛みに対しては、まず炎症によるものかを画像診断などを用いて、適切に評価する必要があります。そのうえで、炎症があると判断された場合には、適切な抗炎症療法が必要となります。
炎症を伴わない痛み
「炎症を伴わない痛み」は、さらに二つに分かれます。
「炎症が起きた後の構造的な変化に伴う機械的な痛み」と「炎症も構造的な変化も伴わない痛み」です。
「炎症が起きた後の構造的な変化に伴う痛み」に対しては、炎症を抑える治療をいくら行っても効果はありません。場合によっては外科的な治療が必要となることもありますし、装具などの作業療法の適応になることもあります。あるいは、鎮痛剤による対症療法が、QOLを守るために必要になることがあります。
構造的な変化がさらに進行してしまうことを防ぐためには、その変化が乾癬性関節炎によるものであるか、その他の要因か(加齢に伴う変形性関節症、腰部脊柱管狭窄症など)を判断する必要があります。乾癬性関節炎によるものであり、その部位の疾患活動性がまだ残っている場合には、炎症を抑える治療を強化することも考える必要があります。
「炎症も構造的な変化も伴わない痛み」は、主に神経や筋肉による痛みです。これらは必ずしも関節の近傍の痛みとは限らず、全身的な痛みを感じることもあります。
全身的な痛みの代表的なものが「線維筋痛症」です。炎症性の病態ではなく、ストレスによって起こる病態と考えられており、筋肉の緊張度が異常に亢進していることが特徴です。力を入れているわけでもないのに筋肉がこわばっており、筋肉の走行に沿って指でおさえていくと強い痛みを感じることで診断可能です。根本的な対応は、早期のストレス要因の除去と考えられます。このためには心療内科や精神神経科の先生のご協力も必要となります。ストレス要因の除去が困難であるために慢性的な病態になってしまうと、鎮痛薬などの対症療法となります。
全体をまとめて、痛みへの対応を考えるときに最も重要であるのは、「体のさまざまな部位に分布する、炎症による痛みを見逃さずに、適切な時期に適切な抗炎症療法を導入し、炎症を最小化する」ことです。これが実行されますと、「炎症を伴わない痛み」を低減できる可能性があります。このためには病状に関して主治医との円滑なコミュニケーションを維持することが重要です。PRO(Patient Reported Outcome;患者さん自身が評価する、現在の状態)のツールを利用することも一つの有効な手段です。
独立行政法人国立病院機構 宇多野病院
リウマチ・膠原病内科 統括診療部長 柳田英寿 先生