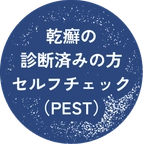長引く関節痛で
お悩みの方へ

関節の痛みは炎症かどうかがポイント
関節の痛みにはさまざまな原因がありますが、大きく分けて「炎症」によるものと「炎症以外」によるものがあります。大切なのは、痛みが「炎症」によるもの(関節炎)かどうかを見分けることです。
炎症があるかどうかで、治療が大きく変わります。痛みが炎症による場合、関節が壊れたり、関節を動かしにくくなるリスクが高く、日常生活に支障をきたすおそれがあります。そのために、できるだけ早い段階での診断と治療が重要です。
なお、痛みの原因については、関節の状態や、血液検査の結果などを総合的にみて医師が判断しますので、痛みが続く場合は、早めに医師にご相談ください。
いろいろある関節痛
関節痛を起こす病気にはどのようなものがあるのでしょうか。ここでは、いくつか紹介します。
乾癬性関節炎
「脊椎関節炎」 をご覧ください。
関節リウマチ
概要・症状
「炎症」による関節の痛みの代表的な病気が「関節リウマチ」です。
関節リウマチの原因は免疫の異常によることはわかっていますが、原因そのものは明らかにされていません。遺伝的な要因に加え、喫煙や歯周病なども関与しているといわれています。
主な症状は、関節の痛みや腫れ、朝のこわばり(関節が固まっているように感じて動かしづらい)などです。症状は、手首や手足の指にみられることが多く、肩、肘、膝、足首などにもみられます。また、左右対称に複数の関節に症状がみられることが多いです。関節の症状が進行すると、関節が変形したり壊れたりします。なお、不思議なことに、関節リウマチでは、首の骨(頸椎)には炎症がみられますが、首から下の背骨(胸椎、腰椎、仙椎)の関節には、ほとんど炎症を起こしません。この後に説明する「脊椎関節炎」と大きく異なる点です。関節以外の症状としては、全身の倦怠感、微熱、食欲低下のほか、皮膚、眼、肺などにも特有の症状がみられます。
検査・診断
関節リウマチの診断は、血液検査、画像検査[レントゲン(X線)検査、MRI、超音波検査など]、痛みや腫れのある関節の数と部位、症状の持続期間から総合的に判断します。血液検査のうち、リウマトイド因子(RF)や抗環状シトルリン化ペプチド(CCP)抗体は、多くの関節リウマチ患者さんで陽性になりますが、必ずしも陽性であっても関節リウマチではないケースや、陰性でも関節リウマチであるケースもあり、注意が必要です。その他の血液検査では、活動性(炎症の状態など)を反映するC反応性蛋白(CRP)や赤沈(ESR)、マトリックスメタロプロテイナーゼ(MMP)-3などが確認されます。
治療
関節リウマチの治療は、免疫の異常を改善する薬物治療を中心に行います。関節の変形や破壊が進行した場合は、人工関節を入れるなどの手術も行われます。
症状が落ち着いているときは、適度な運動を行い、筋力や関節の動きを維持します。痛みなど症状が強いときは、無理をせずに安静にして、関節を守ることが大切です。また、免疫を調整するお薬を使用することが多いため、手洗いやうがいをはじめとした感染症対策はしっかり行います。
脊椎関節炎
概要・症状
脊椎関節炎は、主に首からお尻にかけての背骨(頸椎・胸椎・腰椎・仙椎・仙腸関節)や胸の骨(胸骨・鎖骨・胸鎖関節・胸肋関節)、股関節など、「体軸」といわれる部分の関節が、「炎症」によって痛む「体軸性関節炎」と、主に手足の関節が「炎症」で痛む「末梢性脊椎関節炎」に分けられます。
脊椎関節炎は、さらに次の7つに分けられます。小児を除き、強直性脊椎炎のみ「体軸性関節炎」に含まれます。
①強直性脊椎炎
②乾癬性関節炎
③反応性関節炎
④炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎・クローン病)に伴う関節炎
⑤急性前部ぶどう膜炎(眼の炎症)に伴う脊椎関節炎
⑥分類不能関節炎(掌蹠膿疱症性骨関節炎、SAPHO症候群など)
⑦小児の脊椎関節炎
脊椎関節炎は、40歳以下といった若い男性に発症しやすいとされています。また、肥満、糖尿病などの生活習慣病を合併することもよくあります。
特徴的な症状としては、じっと安静にしても治らないけれど、動くと改善する腰や背中の痛みがあり、その痛みは3ヵ月以上続きます。手の指や肩などに痛み、腫れ、こわばりといった症状もあらわれます。手や足の痛みは左右非対称にみられます。「付着部」と呼ばれる靭帯や腱が骨に付いている部位に炎症が起きることも特徴的です。
脊椎関節炎は、「炎症」による病気のため、発熱やだるさ、さらには乾癬、炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎・クローン病)、ぶどう膜炎といった関節以外の症状を伴う患者さんもいます。進行すると首や背中、腰といった関節の動きが悪くなり、動かしづらくなることがあります。また、関節の柔軟性が損なわれるため、骨折に注意が必要となります。
検査・診断
脊椎関節炎の診断では、症状、血液検査、画像検査[レントゲン(X線)検査、MRI、関節超音波検査]、家族に同じ病気の方がいるかどうか(家族歴)などを確認します。非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)という種類の鎮痛薬が効くかどうかも判断材料として使うことがあります。
血液検査では、ヒト白血球抗原の一つの型であるHLA-B27や炎症に関係するC反応性蛋白(CRP)が陽性になることがあります。一方、関節リウマチに特徴的なリウマトイド因子(RF)や抗環状シトルリン化ペプチド(CCP)抗体は陰性です。
治療
脊椎関節炎のタイプを確認したら、それに合った薬物治療やリハビリテーションなどの運動療法を行います。生活に支障をきたす場合は、手術も検討します。乾癬、ぶどう膜炎、炎症性腸疾患といった関節以外の症状に対しては、それぞれの専門医と連携して治療を行います。
線維筋痛症
概要・症状
線維筋痛症は、「炎症以外」の原因で関節や筋肉に痛みを感じる病気です。その代表的な症状は、針で刺されたような全身の痛み、筋肉のこわばりです。この痛みが3ヵ月以上続くことで、仕事や家事ができない、眠れないなど、日常生活に大きな支障をきたすことがあります。また、痛み以外の症状として、動悸、呼吸困難感、下痢や便秘、手足のしびれなどがみられることもあります。
線維筋痛症の原因はまだ明らかにされていませんが、精神的・肉体的なストレスが発症に関係していることが多いと考えられています。ただし、痛みの原因は、痛む部位自体にあるわけではなく、脳の“痛みを感じる仕組み”が過敏になっているために、軽く触れただけでも強い痛みを感じてしまうと考えられています。さらに、免疫系の異常が関わっている可能性も指摘されています。
検査・診断
線維筋痛症は、血液検査や画像検査をはじめとして、さまざまな検査を行っても、患者さんに共通した特徴的な異常がみられないために、診断が遅れてしまうことがあります。診断基準・分類基準を活用しながら、症状の内容とその経過を細かく診察することによって診断されます。
治療
線維筋痛症は、原因が明らかではないため、完治させる治療法はありません。そのため、まず大切なのは、患者さん自身が線維筋痛症であることを受け入れ、正しく理解することです。治療は薬物治療を中心に行われますが、痛みを完全になくすことは難しく、日常生活に影響が出ない程度にまでコントロールすることを目指します。また、薬物療法と併せて非薬物療法も行われます。非薬物療法には、運動療法と精神・心理療法があります。運動療法は、体に負担の少ない水中運動や太極拳などの有酸素運動が勧められます。精神・心理療法では「認知行動療法」が行われます。認知行動療法とは、ストレスなどの影響で視野が狭くなってしまった考え方や行動のパターンを、患者さんご自身の力で少しずつ和らげ、より自由で前向きな考え方や行動に変えていけるように、医師や臨床心理士などがサポートする治療法です。不安や抑うつ状態が強い患者さんに勧められます。
線維筋痛症は生命に重大な影響を与えることはなく、この病気が直接の原因で命を落としたという報告はありません。
しかし、長期間にわたって診断がつかず、激しい全身の痛みが続くと、精神的な負担や生活への影響が非常に大きくなることがあります。その結果、社会生活が著しく制限されてしまうケースも少なくありません。
変形性関節症
概要・症状
変形性関節症は、「炎症以外」の原因で関節が痛む代表的な病気です。関節の軟骨がすり減ることで、クッションの役割が弱まり、骨同士がぶつかるようになり、痛みが生じます。
よく知られているのは膝の痛みですが、手の指、股関節、背骨などにも起こることがあります。手の指の場合は、指の第一関節に起こることが多く、関節が盛り上がってごつごつした感じになります。
軟骨がすり減る原因は明らかにされていませんが、加齢、力による負担、ホルモンの分泌の変化、さらには、炎症が関与している可能性も指摘されています。なお、変形性関節症では、軟骨だけでなく、その下の骨や靭帯など関節全体も変化していきます。
検査・診断
診断にはレントゲン(X線)検査が用いられます。ただし、痛みの強さと関節の変形の程度は必ずしも一致しません。
治療
軟骨の減少はゆっくり進行するため、ほとんどの場合は積極的な治療は不要です。しかし、生活習慣の見直しはとても大切です。加齢や日々の生活で生じる負担など、避けられないものはありますが、例えば膝の変形性関節症の場合、肥満が膝への負担になっていることがあります。その場合は減量のために、食生活の改善に加えて、膝に負担のかからない運動(ウォーキング、水中運動など)が勧められます。また、関節への負担を減らすために、関節を支える筋力を強化するリハビリテーションも行われます。
変形性関節症では、減少した軟骨そのものを増やすような治療で保険適応されたものはありません。対症療法として、関節を保護するために、関節内へヒアルロン酸を注入することがあります。痛みに対しては、消炎鎮痛薬を使用します。
生活の改善や薬物療法によっても、痛みが十分に抑えられず、日常生活に支障をきたす場合は手術が検討されます。軟骨が大きく減少してしまった場合は、人工関節を入れる手術が行われることもあります。
痛風
概要・症状
痛風は、痛みがとても強いことから「風にあたるだけでも痛い」と言われ、その名がつきました。体内で過剰に作られた尿酸という物質が結晶化して関節内にたまり、炎症を引き起こすことで生じる病気です。
症状として多いのは、足の親指の付け根の関節に起こる痛みです。そのほか、膝、手、肩の関節にも痛みがみられることがあります。痛みはずっと続くのではなく、突然発作のようにあらわれ(痛風発作)、通常は数日でおさまります。
検査・診断
診断は、炎症を起こしている関節から関節液を採取し、尿酸の結晶が認められれば痛風と確定されます。ほかに、血中の尿酸値や、関節に対する超音波検査から診断することもあります。
治療
治療は、薬物療法と生活習慣の改善が基本になります。
薬物療法では、強い痛みを抑える消炎鎮痛薬と、血中の尿酸値を下げる薬が使われます。
生活習慣の改善としては、食べ過ぎを抑え、尿酸の原料となるプリン体を多く含む食品(肉や魚の内臓)やビールなどアルコール飲料を控えます。尿酸の排出を促すために水分はしっかりとることが大切です。激しい運動は尿酸値の上昇を引き起こすことがあるため、運動する場合はウォーキングなど軽めなものを行います。また、痛風発作を起こしているときは、安静にして、患部を冷やします。